施主検査は、マイホームの引き渡しの直前にある最終確認になります。我が家の指摘箇所は40か所くらいで下が多いのか少ないのか分かりませんが、いろいろと準備してよかったなと思いましたのでそれを書いていきたいと思います。
引き渡し時にも確認はできますし、それ以降に気になる点があれば修正してもらうことも可能だとは思います。修正が引き渡し後になってしまうと、修正に対してた違いが必要になるのが不便な点ですね。そのためしっかり修正してもらってから引き渡しを受けられるように頑張りましょう。
施主検査より前にできるだけ確認する
施主検査で確認する要素は非常にたくさんあります。施主検査で確認して発見したものについてはもちろん直してもらえますが、完成したものを大幅に変更する(床板をはがす、壁をはがすなど)と家を傷めることもあるので注意しましょう。施主検査で確認するところはとにかくたくさんあるので、後を楽にするためにも事前に確認できるところはしておきましょう。
基礎完成や上棟後
この時点で確認できるものといしては間取りが図面と合っているかだったり、柱や壁の位置が予定通りか同課などが確認できると思います。壁補強する部分には追加の板が張られたりするのでそういうのも確認しておくといいですね。
内側の壁施工時
断熱材や電気配線をした後に、内側の壁板が張られます。内壁を壁が張られてしまうと見えなくなってしまうので、断熱材がしっかり入っているかや、電気配線が想定通りのところにあるかは事前に確認しておきましょう。
- 窓のデザインや色が合っているか
- 玄関ドアのデザインにゃ色が合っているか
屋根や外壁施工時
屋根や外壁は外から確認することができるので事前に確認しておきましょう。屋根の場合は瓦の色やデザインが合っているか、は風雨の部分が想定通りになっているかなどを確認しましょう。
- 外壁の色分けしている方はそれが合っているか
- 屋根の形状は合っているか
施主検査直前
どんどん家ができてきて楽しいころだと思います。床以外については大体できていると思いますのでさらにどんどん確認していけると思います。
- 床材や壁紙
- 建具のデザインや色
- 照明の位置
- キッチンのデザインやカップボードの形状が仕様書通りか
- 雨樋の位置や色は予定通りか
施主検査の準備
いよいしょ施主検査になりますのでしっかり準備しておきましょう。記憶だけで確認するとどうしても漏れてしまうと思いますので、これまでの資料などを有効活用してしっかりチェックしていきましょう。
資料を用意する
- 最終の間取り図(細かく指定したものなどが書いてあるもの)
- 電気図面(コンセントの位置や照明、スイッチの位置の確認)
- インテリア関連(壁紙の色や、水回りの色などを選択したものの確認)
- タマリビング関連(カーテンやエアコンなど)
上記のような資料はしっかり用意しておきましょう。それ以外には注文したオプション一覧についても自分で作成するのもおすすめです。契約書のオプション一覧もそうですが、キャンペーンやサービスでつけてもらったものの一覧も作成して確認する必要があります!
道具を用意する
施主検査では確認しやすいようにツールを用意しておくことも重要です。確認できるものがほとんどだと思いますが、一部トラブルで未完成の部分があるかもしれません。そういうところは未確認である印をつけて、引き渡し時に忘れずに確認するようにしましょう。
- 懐中電灯(電気が通っていないことがあったり、暗いところを照らすことができる)
- メジャー(サイズや位置を指定したものが合っているかを確認する
- ボールペン(資料で確認したものに印をつける)
- パチンコ玉や水平器(あればですが、傾きなどを確認できます)
- 自撮り棒(天井裏や床下などを確認するときに有効です)
いざ施主検査
引き渡しを早くしたいと思うとどうしても全部が完成しているわけではないのでそこは認識しておきましょう。早い引き渡しのほうが、賃貸の家賃が少なく住んだりするメリットもあると思います。
完成していないのに引き渡しなんて嫌です!サインなんてしません!という方の場合は、担当営業さんに事前に伝えておかないと、勝手に引渡日が決まってしまうと思います。
大枠の確認から
好きな順でいいと思いますが、大きな要素から確認して、小さな要素をその後見る方が無駄が少ないと思います。まずは資料通りになっているかの確認ですね!
間取り図から行くと、
- 壁や通路の位置
- 間取り図に追記した位置やサイズ
- 垂れ壁や可動棚がついているか
電気図面を見ていくと、
- コンセントの位置とデザイン
- 照明の位置や種類
- スイッチの位置
- 24時間換気や、分電盤の位置
仕様書を見ていくと、
- 指定した設備が入っているか
- 選択した色やオプションがあるか
- 指定したサイズになっているか測る
細かいところの確認
資料に照らし合わせて確認が終わったらわ細かいところをチェックしていきましょう!
まずは全ての扉や鍵を開閉してみで違和感がないか確認したり、扉や窓に傷や汚れがないか確認しましょう。
あとは壁紙の汚れや隙間がないかを確認して、少しでも気になったところは現場監督に伝えてマスキングテープを張ってもらいましょう。
床は手を当てながら確認していったほうがいいかなと思います。作業時はカバーしてくれていると思いますが、特に隅っこの部分は汚れや傷がついていることが多かったです。
外装についてもぐるっと一周確認しましょう。
- 外壁やサッシに傷がないか
- シーリングの隙間や施工漏れがないか
- 家の裏の壁や排気口なども確認しましょう
我が家は指摘箇所は40箇所くらいでした
多いのか少ないのかはわかりませんが、指摘した個所は以下のようになりました。
- 壁紙の汚れや傷10か所
- 壁紙の隙間や破れ10か所
- 床の汚れや傷5か所
- サッシの汚れ5か所
- コンセントの色間違い5か所
- カップボードのドアが傾いて開けにくい
- トイレのドアが開閉しにくい
- 玄関収納のデザインが違う
とにかく可能な限り事前にチェックしておくのが一番重要だと感じました。施主検査の中で大きな間違いを見つけてしまうとショックが大きく、細かいところまで頭が回らなくなるからです。
指摘箇所にマスキングテープを張ってもらったので、修正後の確認のためにスマートフォンで動画撮影をしておくのがおすすめです。家をぐるっと1周回りながら、指摘箇所を指摘理由を音声に残しながら全て撮影しておくと、修正箇所のマスキングテープがなくなってしまうこともあると思いますのでしっかり確認できますし、ひとつひとつメモを取るのも大変なのでやはり動画がおすすめです。


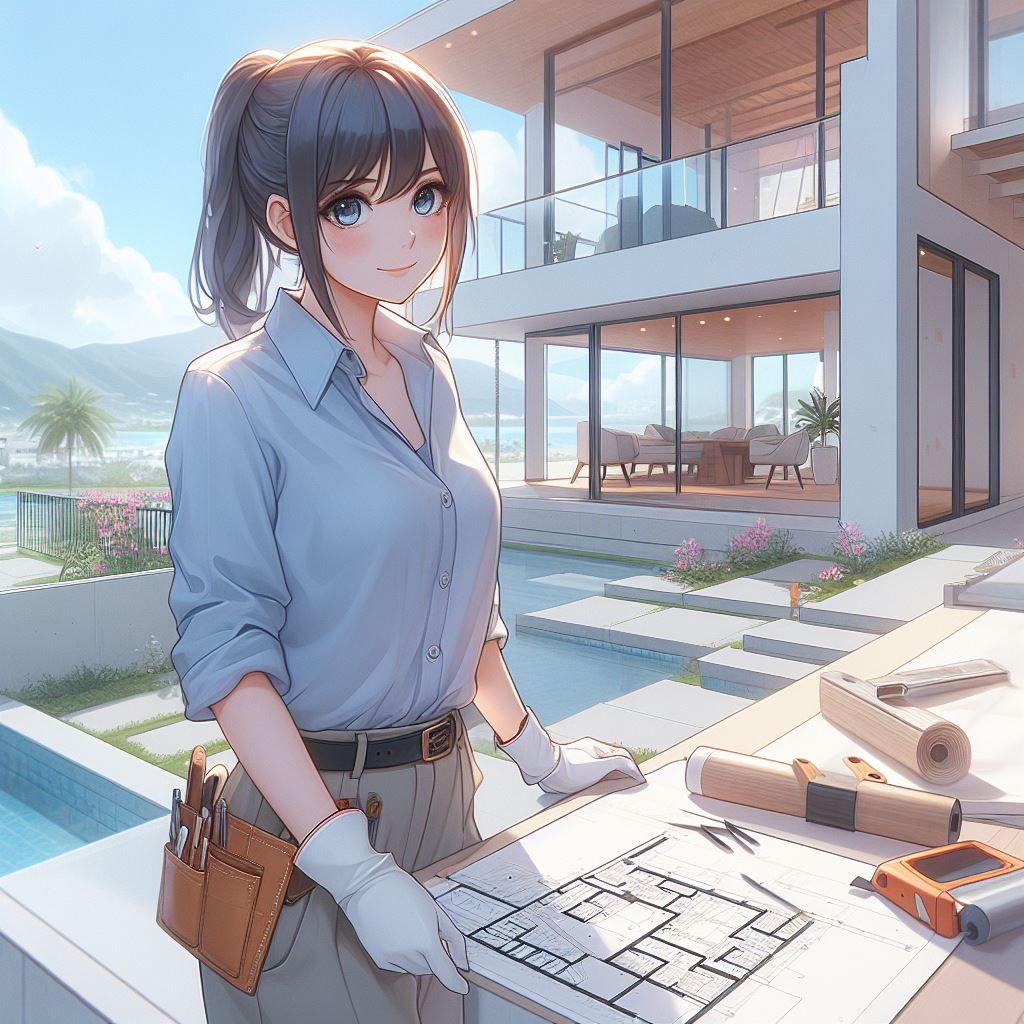
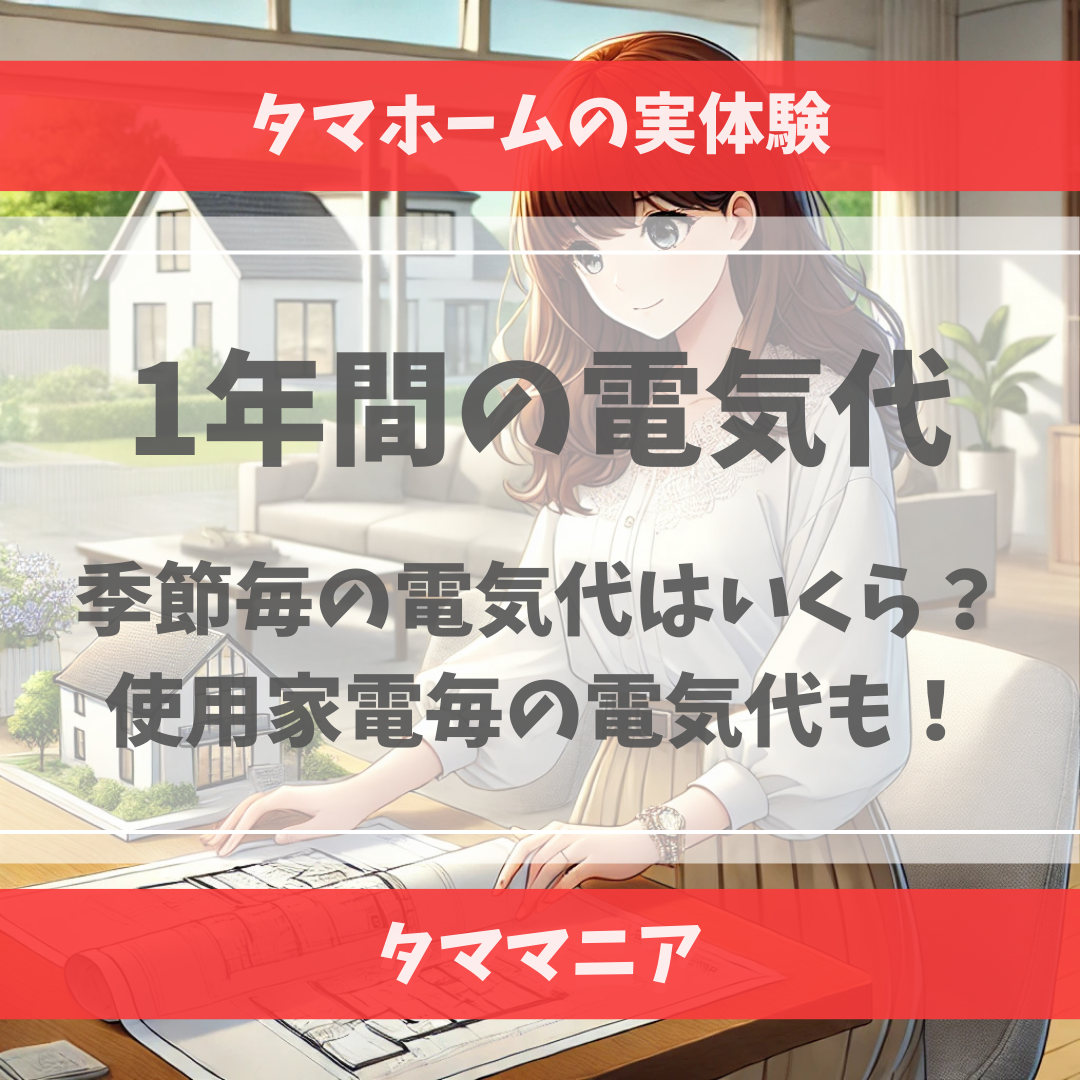
コメント